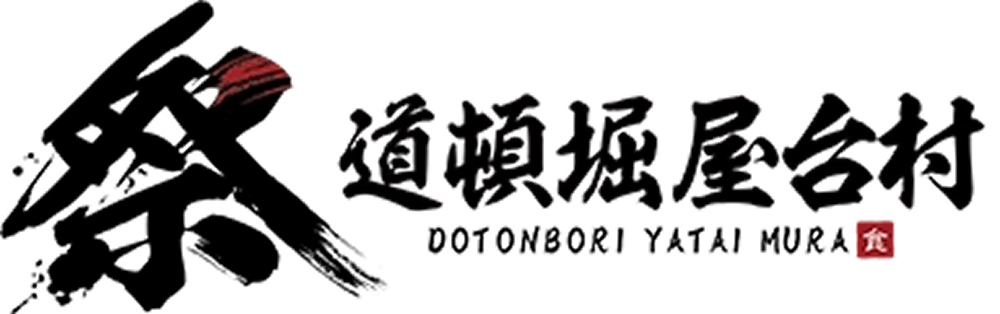ワッショイの謎、解けますか?――なぜお神輿は揺らすのか?祭りに隠された“神さまとの距離感”

祭りといえば、威勢のいい掛け声とともに町を練り歩くお神輿(みこし)。
道頓堀屋台村祭でも、ミニ神輿や法被姿のスタッフが**“祭りの雰囲気”を再現**してくれていますが、実際の伝統的な祭りでは、なぜ神輿をあんなに激しく揺らすのでしょうか?
「壊れないか心配になるレベル…」
「揺らして運ぶのって、実は非効率じゃ?」
――と思ったこと、ありませんか?
今回は、そんな素朴な疑問に迫るお神輿“揺らし”の理由と意味を、わかりやすくご紹介します!
■ 神さまを“楽しませる”のが第一の理由!
お神輿とは、もともと神さまの乗り物。
神社に祀られている神霊を一時的に神輿に遷し、町の中を巡ることで土地全体を清め、福をもたらすという役割を果たします。
その際に激しく揺らすのは、「神さまに退屈させないようにするため」。
昔の人々は、神さまにも**“ワイルドな乗り心地”の方が楽しいだろう!**と考えたのです。
つまり、あの揺れはおもてなしの演出だったんですね!
■ 神さまの力を“目覚めさせる”という説も
また、神道の考えでは、祭りの最中に神さまの霊力を活性化させるという意味もあり、神輿を揺さぶることで眠っている力を奮い起こすという側面もあります。
ドンドコと太鼓を鳴らし、「ワッショイ!」と掛け声をかけるのも、神さまに対する音と動きによる刺激。
つまり、神輿を揺らす=神さまを元気づけるアクションというわけです。
■ ワッショイの語源も「和を背負う」!?
ちなみに、お神輿担ぎの際によく聞く掛け声「ワッショイ(和ッショイ)」には、
「和(わ)を背負う」=地域の一体感
「良い事を背負ってくる」
という意味があるという説があります。
つまり、担ぎ手たちは神さまのご利益だけでなく、地域の願いや希望を一緒に運んでいるのです。
あのエネルギーは、人と人、そして神とのつながりそのものなんですね。
■ 道頓堀屋台村祭でも“祭りの心”を体感できる
道頓堀屋台村祭には、大型の神輿こそありませんが、提灯や法被、太鼓、屋台グルメなど、すべてに“祭りのエッセンス”が詰まっています。
なかでもスタッフの法被姿×太鼓演奏×和の音楽は、まるで神輿の練り歩きのような熱気!
イベントによっては、和太鼓体験や舞台演舞もあり、まさに“参加型のお祭り気分”を楽しめます。
揺らす意味を知ると、お神輿がもっと面白くなる!
次にどこかでお神輿を見かけたら、ただの騒ぎに見えるその動きの中に、
「神さまへの気遣い」や「町の願い」が込められていることを、ちょっと思い出してみてください。
そして、道頓堀屋台村祭ではそんな“伝統の心”を、気軽に、日常の中で楽しむことができるんです。
五感で感じる祭りの空間――
揺れないけど、心が揺さぶられる体験が、ここにあります。